好事門を出ず 悪事千里を行く
意味:良い評判は広まりづらく、悪い評判は広まりやすい
蜀の宰相の韋莊が、科挙(役人になる試験)を受けようとしていた若い頃、黄巣の乱が起こり、都が攻められた。その際、彼は「秦婦吟」という詩を作ったが、その中の一節に、「内庫焼かれて錦繍灰となり、天街踏み尽くす公卿の骨(宮中の宝物庫は焼かれてきらびやかな織物は灰となり、都の大通りには高官の骨が踏み尽くされた)」という激しい表現があり、後に多くの高官たちがこの詩を見て驚き、眉をひそめた。韋莊はそれを恥じて、その詩を口にすることを避けるようになった。当時の人々は彼を「秦婦吟の秀才」と呼んだ。後年、韋莊が家訓を作った際には、「秦婦吟を屏風などに書いて飾ることを禁ず」と明記し、誹謗を防ごうとしたが、すでに遅かった。
晋の宰相の和凝も、若い頃に曲子詞(艶やかな詞)を好んで作り、汴京や洛陽に広まっていた。後に宰相となった彼は、それらの詞を回収して焼き捨てるよう人に頼んだが、追いつかなかった。彼は徳のある重厚な人物だったが、結局その艶やかな詞によって名誉を損なわれた。異民族の契丹が汴京の城門に攻め入った際には、彼を「曲子相公(艶やかな詞の宰相)」と呼んでさげすんだ。
まさに「好事門を出ず、悪事千里を行く」という言葉通りである。士君子(立派な人物)たる者は、このことを戒めとすべきである。
『北夢瑣言』
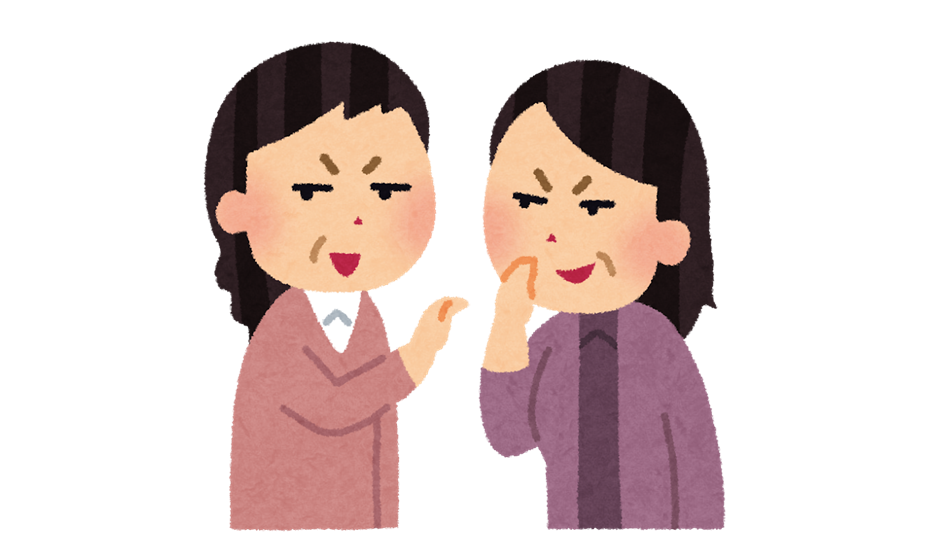



コメント