匹夫の勇
意味:感情にまかせた考えなしのつまらない勇気
斉の国の宣王が孟子に尋ねた。「隣国と付き合うのに、良い方法はあるか。」孟子は答えて言った。「あります。仁のある者だけが、自分が大国であっても小国とよく付き合うことができます。だから昔の湯王は葛とよく付き合い、文王は混夷とよく付き合ったのです。また、智のある者だけが、自分が小国であっても大国とよく付き合うことができます。だから昔の周の大王は匈奴とよく付き合い、句践は呉とよく付き合ったのです。大国でありながら小国とよく付き合うのは、天を楽しむ者です。小国でありながら大国とよく付き合うのは、天を畏れる者です。天を楽しむ者は天下を保つことができ、天を畏れる者は国を保つことができます。『詩経』にも、『天の威を畏れて国を保つ。』とあります。」
王が言った。「立派な言葉ではある。しかし私には悪い癖がある。私は勇を好むのだ。」孟子が答えて言った。「王様は小さな勇を好んではなりません。剣を握り、目を怒らせ、『あいつなど敵ではない。』などと言うのは、いやしい男の勇であり、一人を相手にする程度のものです。王様は大きな勇を持ってください。『詩経』には『王が真っ赤になって怒り、軍を整えて、莒への侵略を防ぎ、周の国の幸福を厚くし、天下を安心させた。』とあります。これぞ文王の勇です。文王は、ひとたび怒ることで天下の民を安心させたのです。また、『書経』には『天が民をつくったとき、君主を立て、師を立てたのは、上帝を助けて民をいつくしむためである。世界中の罪のある者や罪のない者への対処は、ただ私一人が行う。天下の誰もその志を邪魔してはならない。』とあります。天下に無道をする者が現れれば、武王は恥に思いました。これぞ武王の勇です。武王もまた、ひとたび怒ることで天下の民を安心させたのです。さて、王様も、「ひとたび怒ることで天下の民を安心させる」という大きな勇をお持ちなのであれば、むしろ民の方が王に勇を嫌いにならないでほしいと思うほどでしょう。」
『孟子 梁恵王章句 下』
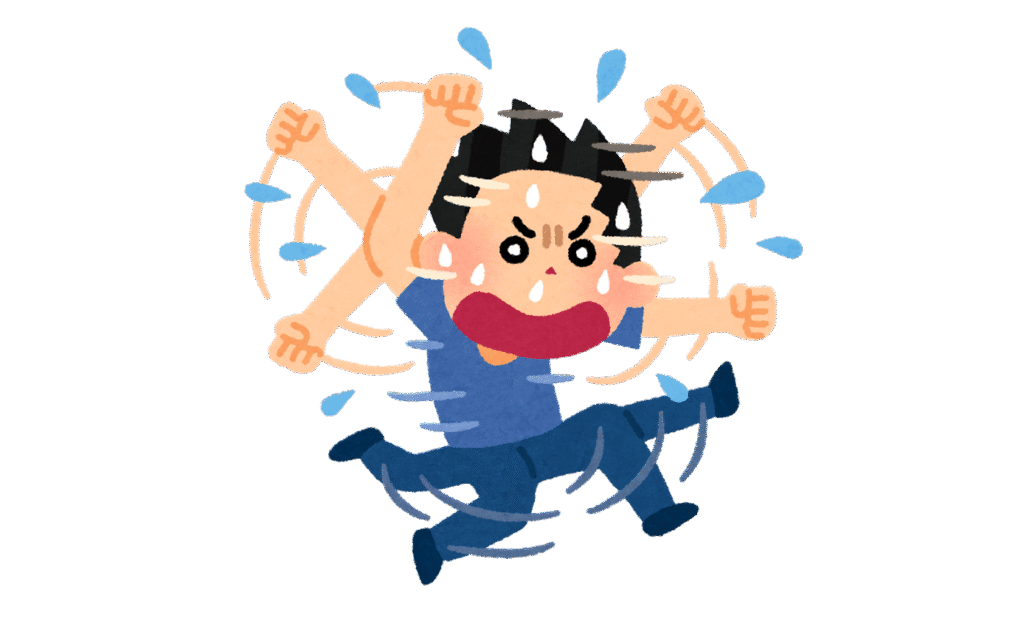


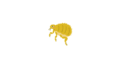

コメント