一字千金
意味:立派な文章や文字
秦の国の荘襄王(子楚)は即位して三年で亡くなり、太子の政(後の始皇帝)が秦王となった。政は呂不韋を尊んで相国(宰相)に任じ、仲父(父に次ぐ者)と呼んだ。秦王はまだ若く、母の太后は、時々ひそかに呂不韋と通じていた。呂不韋の家の召使いは一万人もいた。
この当時、魏の国には信陵君、楚の国には春申君、趙の国には平原君、斉の国には孟嘗君という人物がいた。四人とも優れた人物に対してへり下り、食客として養うことを好み、競い合っていた。呂不韋は、秦が強国であるのに彼らに及ばないのは恥だと思い、優れた人物を招いて厚遇したので、食客が三千人にもなった。
当時、諸侯は多くの知識人をかかえ、荀子の一派などは書物を書き著して天下に広めていた。呂不韋も自分の食客に各自が知っていることを著させ、編集して、八覧、六論、十二紀などの、二十余万言の書物を作った。この書物には、天地、万物、古今のことが備わっているとみなし、「呂氏春秋」と名付けた。秦の都の咸陽の市場の門にこの呂氏春秋を並べ、千金の賞金を懸けて諸侯を旅する人や食客を呼び、この書物から一文字でも増やしたり減らしたりすることができる者がいれば、千金を与えるとした。
『史記 呂不韋列伝』


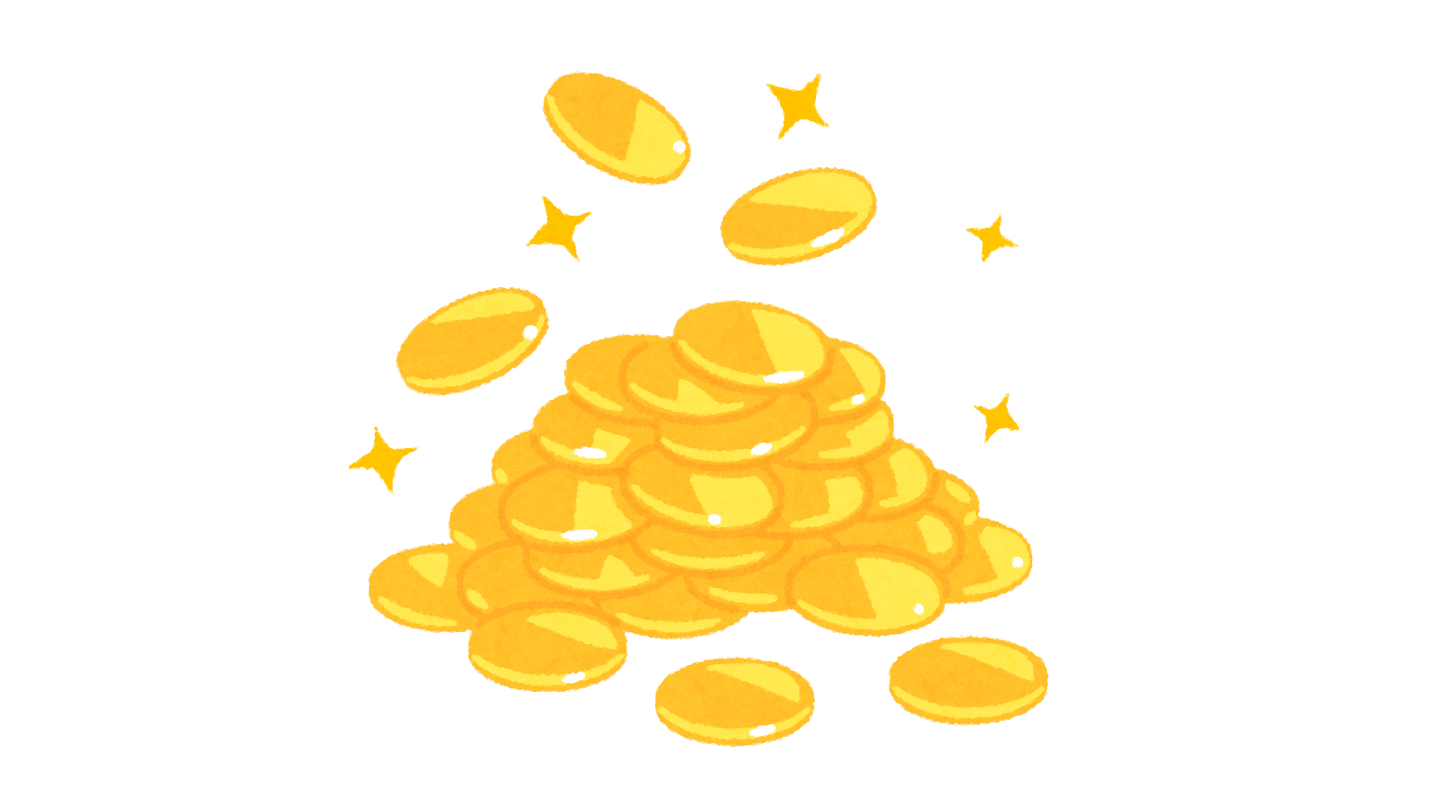


コメント