二柄
意味:君主が人を支配する賞罰の権限
賢明な君主が臣下を制御する拠り所は、二つの柄だけである。二つの柄とは、刑と徳である。何を刑と徳と言うのか。死罪を刑と言い、恩賞を徳と言う。臣下は処罰を畏れて褒賞を喜ぶ。ゆえに君主が自分で刑と徳を行えば、臣下たちは刑の威力を畏れ、徳の利益に従う。しかし、世のよこしまな臣下はそうではない。自分の悪むものを君主の権限を得て罰し、自分の愛するものを君主の権限を得て賞する。今、君主が賞罰の威力と利益を自分からあたえず、臣下の意見を聞いて賞罰を行えば、国中の人がみなその臣下を畏れて君主を易り、その臣下に従い君主から離れるだろう。これが、君主が刑と徳を失うことによる患いである。
そもそも、虎が犬に勝てるのは、爪と牙があるからである。虎から爪と牙をとり、犬にそれを用いさせたら、逆に虎は犬に負けるだろう。君主は刑と徳によって臣下を制御する。もし君主たるものが刑と徳を捨てて、臣下がこれを用いれば、逆に君主が臣下に制御させられるだろう。
田常という人物は、上の者に対しては爵位や俸禄を請求してそれを他の臣下たちにあたえ、下の者に対しては大きな入れ物を使うことで百姓に施しをした。これは、君主である簡公が徳を失って、臣下である田常が徳を用いている例である。このようなことがあったから、簡公は殺されることになった。また、子罕という人物が宋の国の君主に言った。「恩賞を与えることは、民が喜ぶことですから、君主様がご自分で行ってください。死罪や刑罰は、民が悪むことですから、私が行いましょう。」これによって宋の君主は刑を失い、子罕が刑を用いた。ゆえに宋の君主は劫かされた。田常が徳を用いただけで簡公は殺され、子罕が刑を用いただけで宋の君主は劫かされた。
今の世の臣下にいたっては、刑と徳の二つともを用いているのだから、すなわち君主の危ういことといったら、簡公や宋の君主よりも甚だしい。ゆえに劫かされ殺され目を蔽われているような君主は、刑と徳を二つともを失って臣下に用いさせている。そのようにして危険や滅亡を避けられたことは、いまだかつてあったことがない。
『韓非子 二柄』



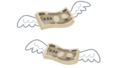
コメント