山に躓かずして垤に躓く
意味:大事は注意するため失敗しづらいが、小事は不注意で失敗しやすい
重い刑罰は人を罰するためにあるのではない。賢い君主の法律は、功罪をよく計算する。賊を治めるとは、功罪を計算し終わったものを治めることではない。功罪を計算し終わったものを治めるのは、死人を治めるようなもので無意味である。盗人を処刑するとは、処刑したものを治めることではない。処刑したものを治めるのは、受刑者を治めるようなもので無意味である。ゆえに「一人の悪人の罪を重くして、国内の邪悪を防止する。」と言われている。これこそが国を治める方法である。重く罰せられるのは盗賊であり、盗賊によって悼み懼れるのは良民である。国が治まることを望む者は、どうして重い刑罰に疑問を持つだろうか。また、恩賞を厚くするというのは、一人の功績を賞するためにあるのではない。国中に推奨するのである。恩賞を受ける者は利益を喜び、賞されていない者は業績をあげようとする。一人の功績に報いることで、国中の民衆に推奨するのである。国が治まることを望む者は、どうして厚い恩賞に疑問をもつだろうか。
今、国を治めることを知らない者はみな、「刑罰を重くすれば民を傷つける。刑罰を軽くしても悪事は止む。どうして重い刑罰が必要なのだ。」と言う。これは国を治めるということが分かっていない。そもそも重い刑罰があるという理由で悪事を止める者は、軽い刑罰があるという理由では悪事を止めるとは限らない。しかし、軽い刑罰があるという理由で悪事を止める者は、重い刑罰があるという理由では必ず悪事を止める。こういうわけで、上に立つ者が重い刑罰を設けると、悪事はことごとく止み、悪事がことごとく止めば、民は傷つかない。いわゆる重い刑罰とは、悪人の利益が小さく、上に立つ者があたえる罰が大きいのである。民は小さな利益のために大きな罪を犯すことはない。だから悪事は必ず止む。いわゆる軽い刑罰は、悪人の利益が大きく、上に立つ者があたえる罰が小さいのである。民は利益を求めて罪をあなどる。ゆえに悪事は止まない。聖人の諺に「山に躓かずして垤に躓く」というものがある。山は大きいため人々が注意するが、垤は小さいため人々があなどるためである。今、刑罰を軽くすれば、民は必ず刑罰をあなどる。罪を犯して罰しないのであれば、国中の人々を駆り立てて見捨てることである。罪を犯して罰するのであれば、民に落とし穴を設けることである。ゆえに、軽い罪というのは民にとっての垤である。罪を軽くするという方法は、国を乱さなくとも、民に落とし穴を設けることである。刑罰を軽くすることこそ、民を傷つけるというべきである。
『韓非子 六反』




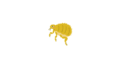
コメント